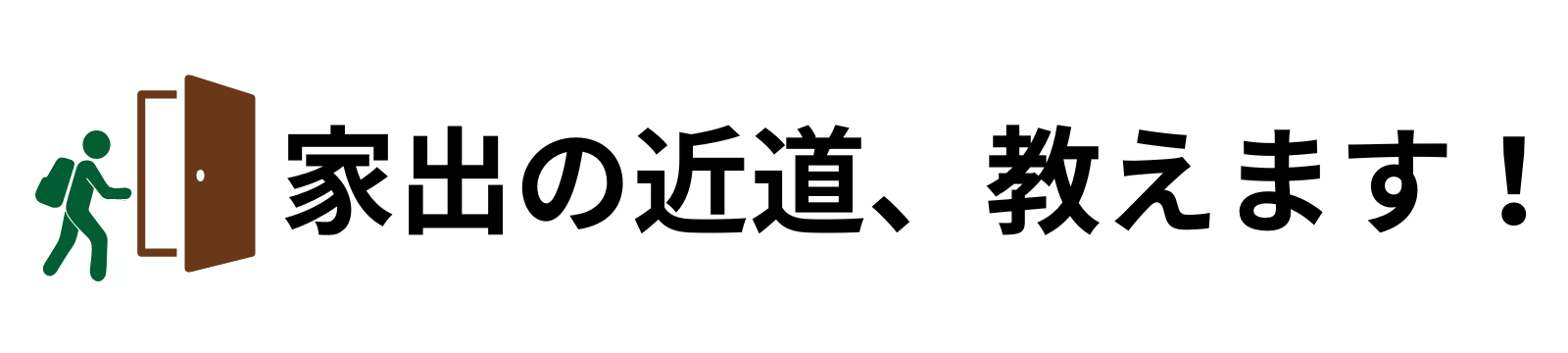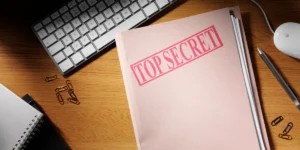家庭内暴力、虐待、ネグレクト、子供の安全が脅かされるような状況があってはいけません。
しかし、もうすでに起きてしまっている場合、お子さんの心や命が危険にさらされている時、「子供を連れて逃げる」という選択肢をとることは、とても大切です。
この記事では、そのような困難な状況に置かれた親御さんに向けて、考えられる複数のパターンと具体的な方法、そして何よりも優先すべき注意点について解説します。
重要な注意点:
- 緊急性と危険性: 子供を連れて逃げる状況は、多くの場合、子供や保護者に深刻な危険が迫っている緊急事態です。
- 法的責任: 親権や監護権を持つ親による子供の連れ去りも、状況によっては違法となる可能性があります。必ず弁護士などの専門家に相談してください。
- 子供の福祉: 何よりも子供の心身の安全と福祉が最優先です。
- 支援体制: 逃げる前に、可能な限り支援してくれる家族、友人、専門機関に相談し、協力を得ることが重要です。
ケース別:子供を連れて逃げるという選択
以下に、具体的な状況と、その際に考えられる行動、注意点、事例を解説します。
ケース1:家庭内暴力(DV)からの避難
配偶者や同居人からの暴力がエスカレートし、子供への心理的、身体的な影響も懸念される場合、一刻も早い避難が重要です。
 トト
トトいつも傷つけられるのは自分。でもお子さんは家族が傷ついているのを見て、心を痛めているケースが、とても多いんだ。暴力がエスカレートすれば他の家族や大切なお子さんももっと深い傷をおうかもしれない。自分やお子さんが、心や身体に傷を負わないように、最善の選択をしてね。
具体的な方法:
- 緊急避難場所の確保: 親戚、友人宅、一時保護施設(シェルター)など、安全な避難場所を複数検討しておきましょう。
- 持ち物の準備: 貴重品(現金、保険証、母子手帳、子供の着替え、常備薬など)をまとめた非常用バッグを準備しておくと、いざという時に役立ちます。
- 逃げるタイミング: 相手の不在時や、第三者の助けが得られる可能性のあるタイミングを見計らいましょう。
- 避難後の連絡: 周りの人に事情を説明するのは、全て落ち着いてからでも大丈夫です。必要に応じて警察(110番)や最寄りの警察署に相談してください。安易に知り合いに連絡するのはとても危険です。
- 法的措置の検討: 保護命令の申し立て、離婚調停、親権の変更などを弁護士に相談し、今後の安全を確保するための手続きを進めましょう。
事例:
- Aさんは、夫の暴力から自分と子供を守るため、手を挙げられたその時、緊急で110番し、警察の勧めで一時保護シェルターへ入りました。その後、弁護士に相談し、保護命令を申し立て、夫との離婚に向けて動き出しました。
- Bさんは、恋人の暴力が子供にも及ぶことを恐れ、NPO法人の運営するDVシェルターに子供と共に緊急入所しました。シェルターに間に入ってもらいながら、恋人との関係を解消し、一時的に住み込みで仕事をして生活を立て直しました。
ケース2:虐待・ネグレクトからの保護
親や養育者からの虐待やネグレクトは、子供の心身に深刻な傷跡を残します。子供の安全を最優先に考え、行動する必要があります。
具体的な方法:
- 第三者への相談: 信頼できる親族、友人、学校の先生、児童相談所(189番)などに、状況を具体的に相談してください。家の中に虐待という事態があることが分かっても、そのことはある意味、自分にとっても日常になってしまい、「逃げる」というところまで気がつくことができないかもしれません。親御さんも一人で抱え込まず、誰かに客観的な意見を求めることも大切です。
- 証拠の収集: 可能であれば、虐待やネグレクトの状況を記録(写真、日記など)しておくと、状況を説明する際に役立つことがあります。
- 法的措置への協力: 児童相談所や家庭裁判所の調査に協力し、子供の安全確保のための措置(親権停止、施設入所など)を求めることも視野に入れましょう。
事例:
- Cさんの子供は、子供の父親でありCさんの夫から、激しい虐待を受けていました。Cさんは専業主婦でしたが、夫が変わらない様子を見て、子供を連れて地域のシェルターに入所。事情により、最初は生活保護を受けて生活を立て直し、パートタイムから仕事をはじめました。
- Dさんは、妻と共に育児放棄をしており、子供が不衛生な環境で生活していることを地域住民より心配されました。自分にとって、育児放棄が当たり前になっていたものの、児童相談所の介入をきっかけに、Dさん自身も専門機関でカウンセリングを受け、子供と一緒に暮らせるよう、自分の問題を解決することや、「子供を絶対に大切に育てる」ことを心に決め、変わるための努力を続けています。
ケース3:海外への避難(国際的な法的問題が複雑に絡むため、専門家の支援が不可欠です)
国際結婚や国籍の問題で、国内だけではさまざまな判断や安全確保が難しく、海外の機関とのやりとりをしなければいけない場合もあります。この場合、国際的な法的問題が複雑に絡むため、専門家の支援を受けることをお勧めします。
事例:
- Gさんは、母国で政治的な迫害を受けており、子供の安全のために日本への難民申請を検討していましたが、認められず、第三国への移住を弁護士と相談しています。
- Hさんは、国際結婚した夫からのDVから逃れるため、子供を連れて一時的に実家に帰国しましたが、夫が子供の引き渡しを求めており、弁護士を通じて国際的な子の奪還問題について相談しています。
一人で悩まず、専門機関に相談を
子供を連れて逃げるという決断は、保護者にとって精神的にも肉体的にも大きな負担を伴います。決して一人で抱え込まず、周囲の支援を積極的に求め、専門家の助けを借りながら、子供の安全を最優先に行動してください。
相談窓口:
- DV相談ナビ: #8008
- よりそいホットライン: 0120-279-338 (24時間対応、性暴力、DV、性犯罪被害者、生きづらさに関する相談)
- いのちの電話: 各都道府県・指定都市にある、悩みを抱える人のための電話相談窓口 (時間や電話番号は各窓口によって異なります)
この記事が、困難な状況にある方々にとって、少しでも情報となり、支援につながるきっかけとなれば幸いです。
※本記事は情報提供を目的としており、具体的な法的助言を提供するものではありません。必ず専門家にご相談ください。