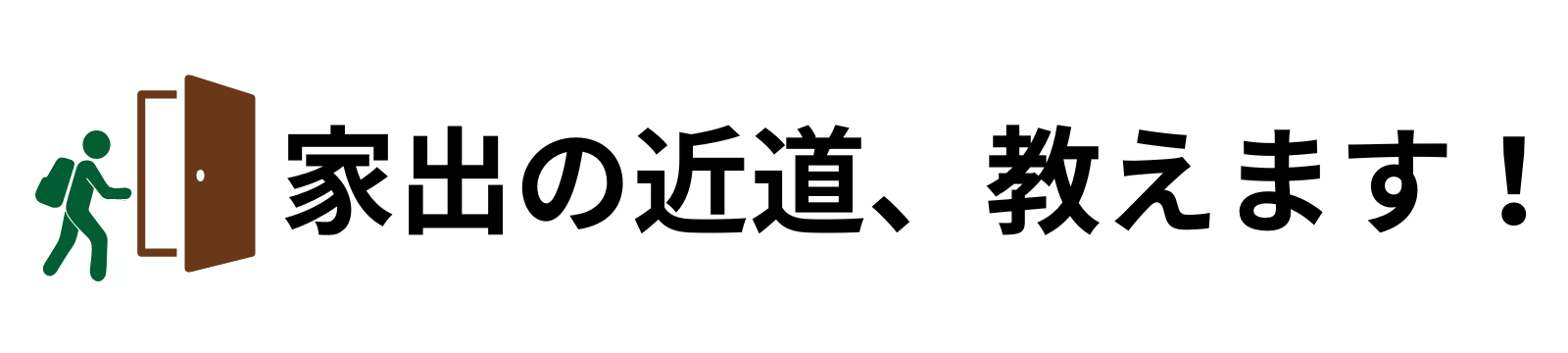「もしかしたら、あの人に住所を知られてしまうかもしれない…」
DV(ドメスティック・バイオレンス)、虐待、ストーカー行為の被害に遭われている方は、常に恐怖と不安を感じていることかと思います。
特に、加害者が同居人や親族の場合、逃げ場がなく、誰にも相談できないと孤立してしまうかもしれません。
しかし、あなたは一人ではありません。
加害者に住所を知られるリスクを減らし、安全な生活を送るための制度があります。
それが「住民票の閲覧制限(DV等支援措置)」です。
この記事では、DV、虐待、ストーカー被害に遭われている方、またはその可能性のある方に向けて、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)の概要、対象者、申請手続き、具体的な支援策などなど・・・詳しく解説します!
 トト
トト閲覧制限の申請のコツや注意点も紹介するよ!
ぜひ最後まで読んでね!
1. 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)とは?
住民票の写しや戸籍の附票の写しは、通常、本人や正当な理由のある第三者が請求できます。
しかし、DV、虐待、ストーカー被害者の情報が加害者に渡ってしまうと、更なる暴力や嫌がらせに繋がる恐れがあります。
そこで、市区町村長が支援の必要性を認めた場合、加害者からの住民票の写し等の交付請求を制限し、被害者の安全を確保する仕組みが設けられました。
これが、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)です。
2. 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)の対象者は?
申請には審査もあるので、一概には言えませんが、対象者は多岐に渡り、例えば以下のような方が支援措置の対象となります。
- 配偶者やパートナーからのDV被害者
- 親族からの虐待被害者(成人した子どもを含む)
- ストーカー行為被害者
- その他、生命や身体に危害を受ける恐れのある被害者
- 上記被害者と同一住所に住む家族
3. DV、虐待、ストーカーの種類
DV、虐待、ストーカーは、身体的な暴力だけでなく、精神的な攻撃や経済的な支配など、様々な形で行われます。
- 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつけるなど
- 精神的暴力:罵倒、脅迫、無視、行動の監視など
- 経済的暴力:生活費を渡さない、お金の使い方を細かく管理するなど
- 性的暴力:性行為の強要、避妊への協力拒否など
- 社会的隔離:友人や家族との交流を制限するなど
- ストーカー行為:つきまとい、待ち伏せ、執拗な連絡など
これらの行為は、あなたの心と体を深く傷つけ、自由を奪うものです。
決して一人で抱え込まず、専門機関に相談することや、その状況を変える(離れる)ためにどんなことができるか、ぜひこのサイトも使って下さい。
4. 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)で制限されることは?
住民票の閲覧制限(DV等支援措置)では、主に以下の3点が制限されます。
- 加害者からの請求制限:加害者からの住民票の写しや戸籍の附票の写し等の請求は、「不当な目的があるもの」と判断され、拒否されます。
- 被害者本人からの請求制限:被害者本人からの請求であっても、代理人や郵送での請求はできません。これは、なりすましを防ぐためです。被害者本人が窓口で請求する場合のみ、交付が可能です。
- 第三者からの請求に対する厳格な審査:第三者(親族や弁護士など)からの請求については、本人確認と利用目的の審査が厳格に行われます。



第三者からの請求に対する厳格な審査については、「絶対守ってくれる」と安心できる自治体もあったし、前向きではない自治体も存在したよ。
第三者への開示は、各自治体判断になるから、役所の担当の人とよく話して、どんな時に開示されるのか、よく知ることが自分を守ることにつながるよ。
5. 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)の申請方法は?
まずはお住まい(引越される方は引越し予定地)の市区町村役所・役場の戸籍担当窓口へ相談してみてください。
相談窓口や必要書類は各自治体によって異なるため、事前に確認することが重要です。
主な流れ
①申請:申出書と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、必要に応じて被害の証拠資料(診断書、被害届など)や、申請場所で陳述書のようなものを書くこともあります。
②審査・決定:市区町村は、提出された書類や必要に応じてすでに相談している警察等への確認を行い、支援措置の要否を決定します。
③通知・共有:支援措置が決定されると、被害者に通知され、関係する市区町村間で情報が共有されます。
相談前に確認しておきたいこと
- 相談窓口の名称と場所
- 相談に必要な書類(本人確認書類、被害状況を証明する書類など)
- 相談の受付時間
- 相談方法(電話、窓口など)
相談時のポイント
- 被害状況を具体的に伝え、支援の必要性を理解してもらう
- 不明な点は遠慮せずに質問する
- 相談内容の記録を取っておく
申請のために行く、主な相談窓口
- 市区町村役所・役場の戸籍担当窓口
- 警察署(生活安全課など)
相談窓口に関する補足情報
各自治体によって、相談窓口が異なっていたり、必要書類が違います。
また、役所・役場、そして警察、どちらも先に電話をして軽く相談をし、その後実際に訪問して本格的に申請のための相談をした方が、スムーズです。
相談回数は平均1回ずつ、滞在時間は1時間〜2時間が平均です。コロナ禍以降、警察署は電話相談を受け付けてくれるところもあるようです。



実は、この制度を利用することに、あまり積極的じゃない自治体もあったんだ。もし、これから引っ越しを考えているなら、閲覧制限の申請に前向きな自治体を選ぶのも一つだよ。
事前に相談窓口に問い合わせて、対応を確認してみると良いかもね。
あなたの安全が第一だから、諦めないで!
6. 住民票の閲覧制限(DV等支援措置)と合わせて利用したい支援制度
- 保護命令制度:裁判所が加害者に対し、被害者への接近や連絡を禁止する命令を出します。
- 緊急一時保護:シェルターなど、安全な場所で一時的に保護を受けることができます。
- 公的機関による支援:カウンセリング、法律相談、就労支援など、様々な支援を受けることができます。
- 民間シェルター:NPO法人などが運営しており。保護施設で、安全な生活と自立に向けた支援を受けることができます。
7. 困ったときの相談窓口
- 警察相談専用電話:#9110
- DV相談ナビ:#8008
- よりそいホットライン:0120-279-338
- 法テラス(日本司法支援センター):0570-078374
- 各都道府県の相談支援センター
まとめ:一人で悩まず、まずは相談を
DV、虐待、ストーカーから離れるには、勇気ある行動が必要です。
逃れたいと思っても、同時に外に出るのことも、怖いと思われているかもしれません。
住民票の閲覧制限(DV等支援措置)は、そんな怖さからあなたの安全を守るための第一歩です。
行動することを怖がらず、怖くてもグッと堪えて、まずは各自治体に相談してみてください!